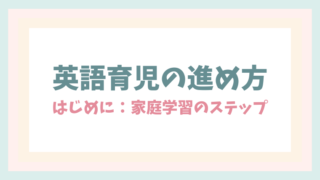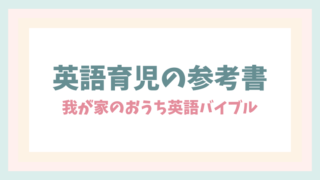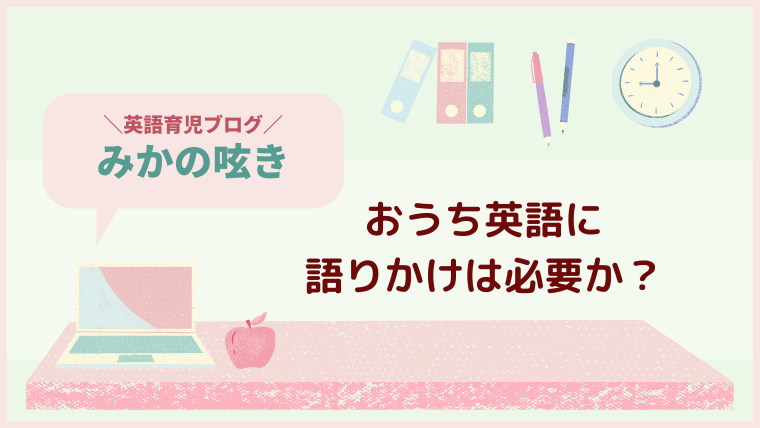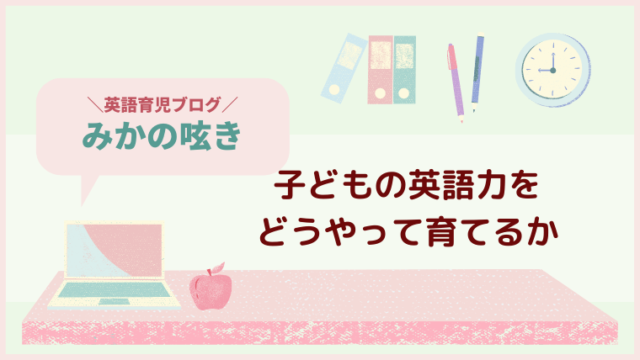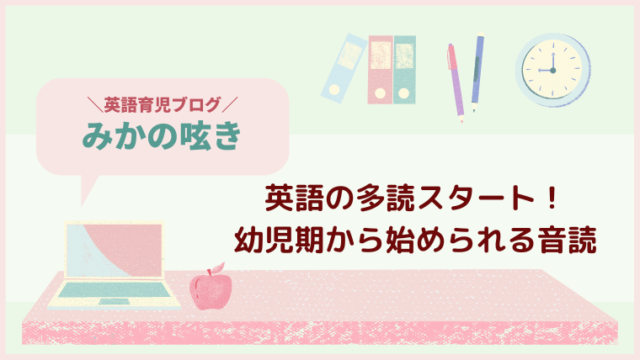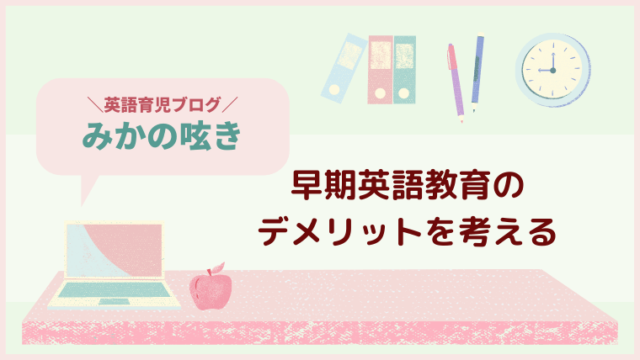おうち英語を始めるにあたり、親から子への「英語での語りかけ」は必要なのでしょうか?
積極的な語りかけを推奨する意見もあれば、必要がないと言い切る専門家もいます。
我が家の場合、母親である私が英語で話すこともできますが、現時点では積極的な「語りかけ」をしていません。
英語での語りかけをしない理由:
- 母語=日本語を最優先
- 家族間のコミュニケーションを重視
- 音読・暗唱もアウトプットと認識
- 英会話は外注可
(オンライン英会話等) - 英語でのアウトプットは焦らない
英語の時間を
一緒に楽しむ意識は忘れない
おうち英語(英語育児)には色々な方法があり、目標レベルも、「英語ができる」のイメージも、家庭によって様々だと思います。
結局のところ、語りかけが必要かどうかも、それぞれが判断すべきところなのでしょう。
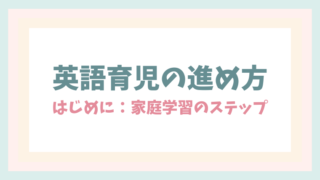
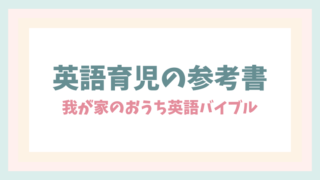
おうち英語と「英語での語りかけ」
おうち英語(英語育児/バイリンガル育児)に関する書籍を開くと、英語での語りかけは必要という意見も、そうでないという意見も目にします。
経験者の声も、様々。
家庭内に二言語が存在する(英語話者がいる)環境ならば、英語でコミュニケーションを取るのはごく自然な流れですし、英語が得意な保護者がそのメリットを活かそうとするのも十分理解できますよね。
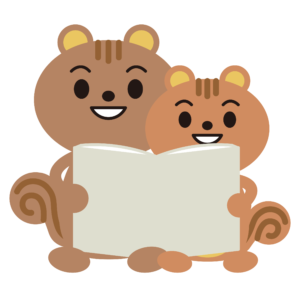
実際に、英語での語りかけを行った方が理解は早まると思いますし、子どもにとっても英語そのものが身近な存在になるという意見にも納得します。
私自身は語りかけをしていませんが、周囲の友人知人で実践している方に理由を聞くと、以下のような声を聞くことができました。
- 親が英語話者である
- おうち英語開始が遅かった
- 親子で英語を学んでいる
- 語りかけ推奨メソッドを実践中
- 英語を「話せる」ようになって欲しい
たとえば英語育児で有名な「タエさん」の著書を読むと、語りかけが有効だったと明確に書かれていますし、彼女の経験を参考に進めたいということであれば、そっくり真似してみるのもいいでしょう。
実際に取り組んでいく中で、親にとっても子どもにとっても、それが必要なのかを見極めれば良いと思います。
なぜ英語での語りかけをしないのか
では、なぜ私が英語での(積極的な)語りかけをしてこなかったのか、その理由を整理してみたいと思います。
日本語を最優先したい
我が家は長女の誕生と同時に「おうち英語」を始めましたが、インターなどに入る予定はなく、日本の教育機関で学ぶことになっています。
そのため、生活言語としても学習言語としても、まずは日本語をしっかり身に付けて欲しいと願ってきました。
もちろん、本人が希望すれば、遠い未来に留学する可能性はあるでしょう。
発話もない時期から毎日英語をかけ流してきたので、正直なところ、早期英語教育のデメリットとして指摘される「母語への弊害」を気にかけていた部分もあります。
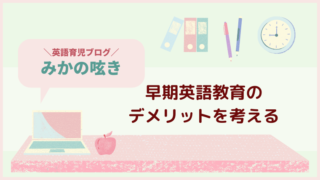
普段の会話を英語にも…となると、我が家の場合は一気にハードルが上がってしまう。日本語を大事に育てたいので会話の中で修飾語とか入れがちだし違う言い回しを繰り返したりもするし、急がなきゃという声かけの時に時計や時間の解説を入れちゃったりするので、ここに英語もぶち込めと言われると…😇
— みか🦖英語育児🦖年少4y+1y (@eigoikuji_blog) December 5, 2022
とにかく、まずは日本語。
第二言語は、第一言語を超えないとも言われていますし、その名の通り「バイリンガル」になって欲しいというわけでもありません。
将来的に、仕事でも学問でも英語を使いこなせるようになってくれれば十分だと思っています(そのレベルまで到達するのも相当大変ですし、最終的には本人の意思が重要になるでしょう)。
家族間のコミュニケーションを大切にしたい
私自身は英語を話すことができますが、娘たちの父親はそうではありません。
家族間のコミュニケーションは大切にしたいので、共通言語は日本語にしたいという思いもありました。
また、私が参考にしている『世界で活躍する子の<英語力>の育て方』をはじめ、高度な英語力を目指すメソッドの多くが、アウトプットよりもインプットを重視しています。
十分なインプットなくして、
アウトプットなし
非ネイティブが語りかける英語は、指示、命令、質問など「冷たい言葉」に偏りがちです。子どもが最初に身につける言葉は「親子の信頼関係をつなぐ架け橋」の役割を持っています。ですから、「愛情のこもった言葉」をたくさんかけてあげることが親子関係を良好にする上でも大切なのです。
子どもの英語教育は、「親が教えるよりも環境に任せた方がはるかに効率的」という意見にも納得しました。
母語や親子関係、あるいは子どもを取り巻く社会の中で、娘たちに影響のない範囲で、たくさん英語に触れさせたいと思っています。
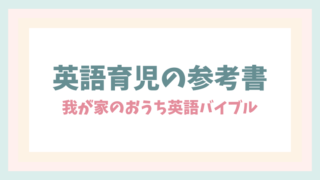
ネイティブの英語を聞かせたい
昔に比べて、英語へのアクセスが非常に簡単な世の中になりました。
英語の教材にしても、絵本にしても、ネイティブの声で読み上げてくれる便利なツールが沢山存在します。
娘たちと並んで座り、絵本を一緒にめくったりはしますが、私が読み聞かせる必要はほとんどなくなりました(日本語の絵本は別です)。
英語での会話表現に関しては、YouTube動画やDVDからも学べるでしょう。
日本にいながらも、家庭内を英語圏のような環境に近づけることは可能だと思っています。

アウトプットは焦っていない
おうち英語を実践している方の中には、「子どもがなかなか英語を口にしてくれない」と心配される方も多いですね。
しかし、英語でのアウトプットが必要になるのは、「今」ではないと思っています。
- インターに入園・入学する
- 英語圏に移住する(留学)する
- 仕事や趣味で英会話力を要される
高校や大学でも、英語でのコミュニケーションスキルが問われる場合もありますし、早期から実技を含む検定試験にチャレンジするのなら、確かに会話スキルも必要になります。
日本語が飛び交う社会で英語を話せれば、周囲には褒められますし、本人にとっても良い自信にはなるでしょう。

しかし、アウトプットが本当に必要とされるのは、もっともっと先のことだと考えています。
そしてこれは重要なポイントになりますが、十分なインプットがないのにアウトプットを求めても、スラスラと自然に出てくるわけがないのです。
インプット > アウトプット
まずは焦らずに、ひたすら良質なインプットを重ねていけばいいでしょう。
実際に、0歳から語りかけなしでも英語を浴びせ続けてきた結果、長女は少しずつ英語を口にするようになりました。
3歳を過ぎるとセンテンスで話すようになり、独り言の9割が英語になっています。
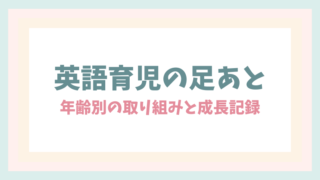
アウトプットの場は外注できる
日本語話者の家庭でも、英語で話す機会を作ることは可能です。その代表格ともいえるのが、オンライン英会話ですね。
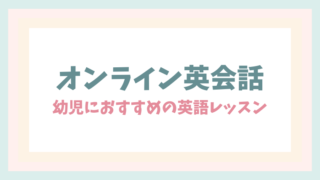
我が家では「おうち英語」の補助的なツールとして、3歳半からレッスンを受講してきました。
実は長女が、英語で会話をしない私に不満をぶつけるようになったことがきっかけとなっています。
ひたすらインプットを続けてきたものの、「アウトプットをしたくてたまらない状態」になったのでしょう。
個人的には、このタイミングまで待っていて良かったと思っています。

このように、我が家では積極的な語りかけをしてきませんでしたが、<英語の時間を共に楽しむ>という気持ちを忘れたことはありません。
CTP絵本の歌を一緒に歌ったり、英語の動画を見ながら一緒に踊ったりということもしています。フォニックスも、親子で学習中。アプリやワークの誉め言葉をあえて英語にしたりということも。
こういった声かけや取り組みを意識するだけで、子どもの英語学習効果がアップするという研究報告もあるそうです。
これからも、親子で無理なく続けやすい方法を探りながら、我が家なりに頑張っていきたいと思います。