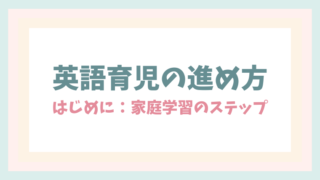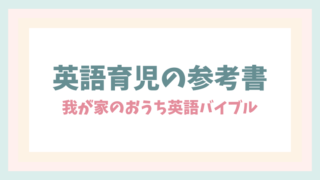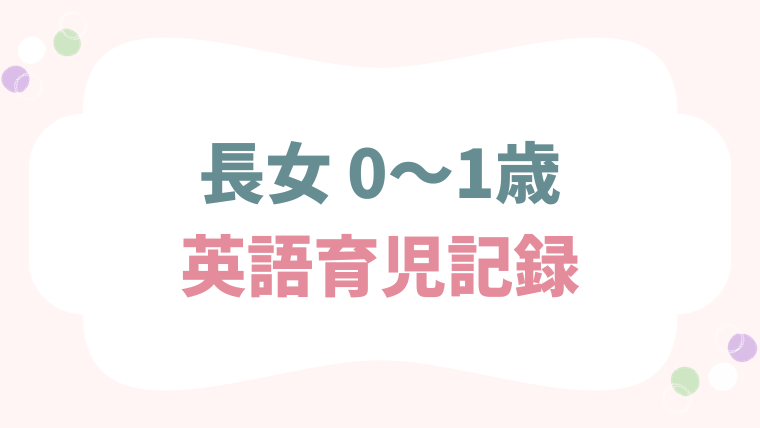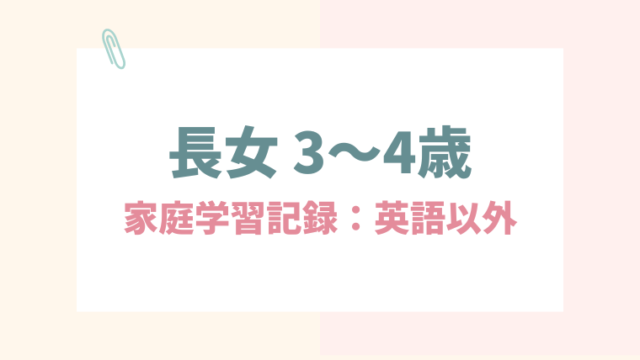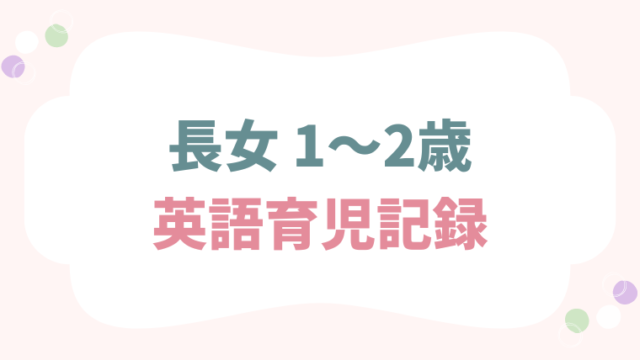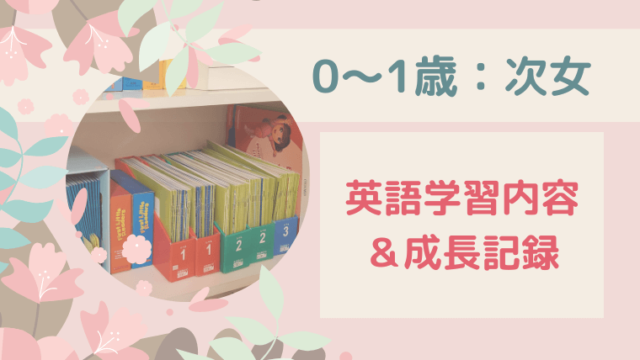妊娠中から子どもの英語教育について情報を集めていたので、長女が生まれたその日から、我が家の英語育児が始まりました。
入院していた産院が個室だったので、赤ちゃんが部屋にいる時間はBGMとしてマザーグースやナーサリーライム(英語圏の童謡)を流してみたり。
無事に退院してからは、慣れない育児と睡眠不足で余裕のない日々が続きましたが、英語のかけ流しなら大きな負担になることはなかったので、あまり気負わずに毎日続けることができました。
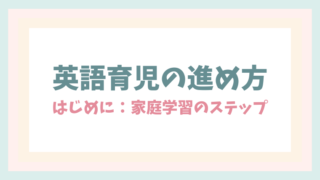
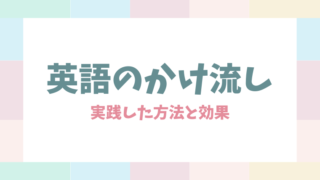
0歳:長女の英語育児と成長記録
赤ちゃんの頃は、さすがに目立った効果と言えるものを感じることはありませんでした。
ただ、言語の区別がつかない時期から英語育児を始めたことで、英語に対する抵抗感を持つことなく育ってくれたことは、シンプルにラッキーだったな…と思います。
また、英語に溢れた生活が「我が家の当たり前」になったことも大きいですね。
- 在宅中は英語のかけ流し
- 動画は英語のコンテンツを厳選
- いつでも手に取れる場所に英語の絵本を
たとえば、「帰宅後は照明をつけるように英語のCDやスマートスピーカーを再生する」「かけ流しのために、英語を再生中は日本語のテレビを見ない」というのは、家族の理解と協力がなければ成り立たない生活だと思います。
しかしこういった習慣を早期から定着したことで、より良いスタートが切れたと思いますし、娘たちも戸惑うことなく、英語に親しみ、英語に触れる時間を楽しんでくれました。

そしてそのような生活を続けていたところ、長女が生後11ヶ月を迎えたあたりから、絵本や図鑑で学んだ英単語を少しずつ口にするようになりました。
ant, apple, ball, car, cat, dog, fish, fox, go, jet, me, mommy, no, oh, up, yummy, zoo など
娘がはじめて英語を口にした時の感動は、今でも忘れることができません。
もちろん、正確な発音とは程遠いものでしたが、英語で言おうとしていることは十分に伝わりましたし、「音とその意味を理解しているのだな」と興味深く観察していました。
それからは、子どもたちが英語でアウトプットする様子を、定期的に記録として残すようになりました。
赤ちゃんの時期から「かけ流し」を習慣化
0~1歳の頃は、英語のかけ流しをメインに行っていました。
幼児の英語学習に関する書籍の多くが、かけ流し(聞き流し)の効果や重要性について解説していたからです。
実際には、科学的根拠や効果ばかりを気にしても仕方がないですし、「視力が発達していない赤ちゃんにできることと言えば、英語を聞かせることくらいかな」と思っていたので、あまり深く考えずにBGMとして流し続けました。
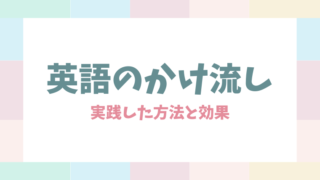
0~1歳の時に聞いたCD
英語特有の音感・リズム感を身に付けるためには、英語圏の童謡(マザーグース/ナーサリーライム)を聞かせた方が良いということで、まとめて聞くことができるCDを用意しました。
こちらの『マザーグースコレクション84』には、ミニ絵本(歌詞ブック)がセットになっています。
歌を聞くだけでなく、歌に関する英語やイラストを見せることで、海外の雰囲気を感じてもらえたらいいな、と思って選びました。

1枚のアルバムを聞き続けると飽きてしまうので、同じように海外の童謡がたくさん収録されているアルバムが欲しくなりました。
そこで、『WEE SING』というベストセラーCDがあることを知り、コスパも良かったので(当時の価格で約1,500円!)気になるタイトルをまとめ買いしました。
- BEST OF WEE SING
- WEE SING FOR BABY
- WEE SING CHILDREN’S SONGS AND FINGERPLAYS
WEE SINGはCDの収録時間がいずれも60分程度に統一されているので、どのくらいかけ流しをしたか、計算しやすく使い勝手が良かったですね。
イギリス英語とアメリカ英語、どちらの英語も聞かせることで、「将来的に困らないよう、リスニング力の強化ができるのでは?」と密かに期待もしていました。

はじめての「英語教材」
娘が1歳になるまでは動画を見せることがほぼなかったので、「歌だけでなく会話も聞かせたい」ということで、アルクのエンジェルコースを購入しました。
現在エンジェルコースは生産終了しており、代わりにリニューアル版として『あかちゃんとママのはじめてえいご』が販売されています。
我が家の教育方針として「まずは日本語を大切にしたい」という考えがあったので、英語での語りかけはほとんどしてこなかったのです。
そのため、CDの中に歌だけでなく、「乳児がいる家庭の会話」や「童話の読み聞かせ」も収録されている点に魅力を感じました。
歌ばかり聞いていると耳が疲れることもありますが、エンジェルコースは他の作業を邪魔することもなく、静かに聞くことができました。
BGMにモーツァルトが採用されているので、リラックス効果があったようにも思います。
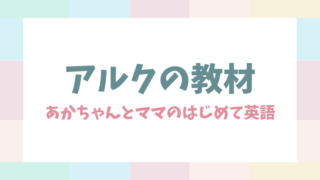
英語が当たり前にある環境を作る
英語圏の家庭環境を真似るように、海外製や英語表記のおもちゃを購入したり、リビングの壁にアルファベットポスターを張ったりと、いつでも周りに英語があるような環境を整えました。
いずれ読むことになる英単語や英文には小文字の方が圧倒的に多く登場しますし、大文字だけでなくはじめから小文字もセットで覚えてしまった方が効率的です。
それ以外は、海外の雰囲気が感じられるものであれば、あまり内容にこだわらなくてもいいと思いました。インテリアとの相性やデザインの好みで選べばいいでしょう。
補足ですが、賃貸の我が家では、壁を傷つけずに何度も貼り直しができる「ひっつき虫」を愛用しています。
実際の使用感としては重めのポスターでも剥がれ落ちることがありませんし、ラミネートしたプリントや写真も綺麗に貼れるので、とても重宝しています。
英語の絵本(ボードブック)
こちらの『Dear Zoo』はとても有名な絵本ですが、しかけも面白くて娘たちも気に入っていました。他にも「ファースト絵本」として人気のタイトルを探しては、YouTubeで読み聞かせ音声があるかを確認してから購入するようにしました。
ただ、日本語が遅れないように気を遣っていたので、絵本に関しては日本語の作品をより多く揃えるように意識していました。
日々の取り組みとしても、日本語の絵本は毎日30冊以上読み聞かせましたが、英語に関しては時々YouTubeの音声を使って一緒にページをめくったり、音声ペンを真似ながら口ずさんだりする程度でした。
タッチペン教材
おもちゃ感覚で楽しめるタッチペンは、聞きたいと思ったタイミングでネイティブの英語を確認できるというメリットがあります。
一般的な書店でも、子ども向けのタッチペン付き英語教材はたくさん並んでいますね。需要があるのか「図鑑」や「絵じてん」は特に多い印象です。
ただ、単語だけでなく頻出フレーズやセンテンスもたくさん聞かせたいと思っていた私には、ベネッセの「はじめてのえいかいわじてん」がとても魅力的に思えました。
タッチペン(音声ペン)で遊ぶことが大好きになった娘は、その後もペン対応の絵本をどんどんめくってくれるようになりました。
早期から取り入れて良かったな、と思います。

英語よりも大切にしたのは日本語
我が家の場合、まずは日本語を優先すべきだと考えているため、英語育児が日本語に悪影響を及ぼさないよう、かなり気を遣いました。
- 英語での語りかけはなし
- 読み聞かせはネイティブ音声
- 毎日 日本語の絵本を読む
- 毎日 日本語で語りかける
特に3歳頃までは、発達面に問題がないか早期に気付けた方がいいと思ったので、私が直接語りかける言葉は母語にすべきと判断しました。
複数の言語を同時に学ばせても、幼児は混乱しない。早期英語教育が母語へ及ぼす影響は、限定的である。
いわゆる専門家の方々がこのように解説していても、娘が日本語を流暢に話し出すまでは少し不安もあったのです。
また、「非ネイティブが語りかける英語は、指示・命令・質問など冷たい言葉に偏りがち」という愛読書内での指摘にも深く頷きました。
娘たちが最初に身に付ける言葉は親子の信頼関係を繋ぐ役割としても重要ですし、できる限り愛情たっぷりの言葉をかけてあげたかったので、英会話(=スピーキング)に関してはいずれ外注すればいいと割り切ったのです。
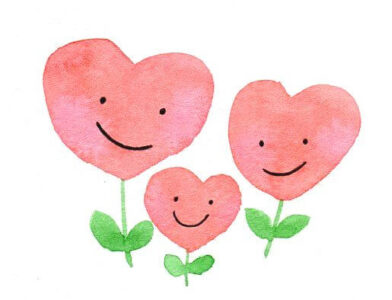
赤ちゃんの頃から日本語を重視してたくさん話しかけ、日本語の絵本を意識的に読み聞かせた効果かは分かりませんが、
娘は日本語の遅れを感じることなく英語もしっかり吸収しているように思うので、このような方針で進めて良かったのかもしれません。
英語育児に関しては様々なメソッドが公開されているので、相性の良い方法を探りながら、各家庭でカスタマイズすることが大切だと思います。